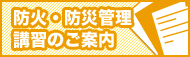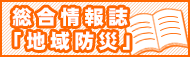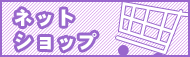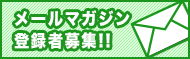兵庫県婦⼈防⽕クラブ連絡協議会

深夜に響く消防⾃動⾞のサイレン。その後続く救急⾞の⾳。
「あ︕ またどこかで⽕災が起きたな」「誰かが怪我をしたのかな」と、最近では⽿慣れてしまった⾳に悲しい想像がよぎる。
毎⽇のようにマスコミを賑わすニュースの中に⽕災による死者も後を絶えず、他⼈事ではないと痛感する昨今です。昔から、家庭の主婦や⺟親達が常に⼼掛けてきたことは、「家族の健康」と「⽕の管理」であったのだが、現代の⺟親の中で「絶対⼤丈夫」と⼦供達に答えられる⺟親が果たして何⼈いるだろうか︖
私は、「それではいけない」、「防⽕に対する⺟親達の意識をもっと⾼めなければ」の実現を図り、賛同は得たものの、ただ⽕災の恐ろしさだけを話すのではなく、「⽕の⼤切さ」「正しい消⽕器の使い⽅ができなくてはいけない」と⼼に決め、すぐに役員組織を作り、会の名称も、夏の陽射しにも強く咲き誇る「ひまわりの花」を象徴して「ひまわり防⽕クラブ」と名付けました。
今まで⽚隅に置かれていた消⽕器を目につきやすい場所へ移動し、656所帯全家族が備え付け、『⽕の⽤⼼は、してきたの︖』を合い⾔葉に⼀丸となって取り組みました。
平成7年の阪神・淡路⼤震災では、いかに⽕事を出さずに家族や街を守り抜いていくのか、不幸にも⽕事になった場合、短時間でいかに適切な対応ができるのかを考えさせられました。⼈間は周りの⼈々と協⼒していかなければ⽣きていけないことを痛感し、常⽇頃から隣⼈たちとの信頼関係を築くことが全ての出発点だと考えるに⾄りました。
さらに、地域の防災⼒を⾼め、市内全域を防災組織で覆いつくすために新たに結成された「⾃主防災組織」は男⼥を問わず⽼いも若きも全てを含んだ住⺠組織となりました。
今後私達に「何ができるか」を、今⼀度⾒直すことが必要ではないでしょうかと考え、私達が住む町「尼崎」から住宅⽕災の発⽣を未然に防ぐために広報活動を徹底し、そしてより⼀層の理解を深めてもらえるように⾝近な所から『⽕の⽤⼼は、してきたの︖』を合い⾔葉に、⾏動⼒のある地域リーダー役を果たしつつ、「魅⼒ある街、尼崎」を目指したいと考えています。
(消防庁機関紙「消防防災/2003-5・夏季号」より転載)